ヤマタノオロチ伝説の正体|なぜ神話に「鉄」が隠されているのか
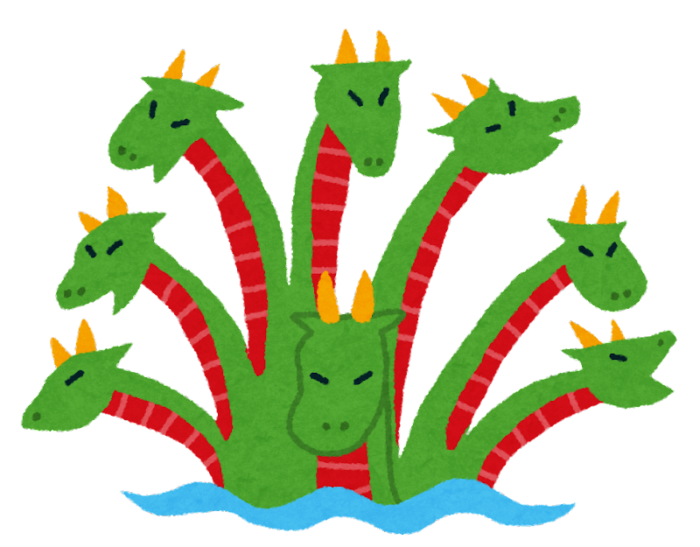
Contents
1.日本の古代神話に見る製鉄技術と自然災害
川上鉄工所は、熱間鍛造(ねっかんたんぞう)の会社です。熱間鍛造を専門に行う会社として、製鉄技術には日頃から関心があります。たとえば、日本ではいつから製鉄が行われてきたか、などです。
古代神話の中には、古代日本の製鉄技術を暗に示唆する物語があります。
八つの頭と尾を持つ大蛇ヤマタノオロチ(八岐大蛇)の物語がそうです。
この神話は、日本の古代文化において特に製鉄技術と深い関りを持つと言われています。
2.ヤマタノオロチの物語に隠された自然災害への恐れ
ヤマタノオロチの物語とは、スサノオノミコト(須佐之男命)が恐ろしい大蛇を退治するという神話です。出雲(現在の島根県)を中心に語り継がれてきました。出雲の神話は『古事記』や『出雲国風土記』に記され、天照大神(アマテラスオオカミ)の弟であるスサノオノミコトや全国平定の神であるオオクニヌシなどが登場します。
ヤマタノオロチは、一つの胴体に八つの頭と尾があり、目はホオズキのようにまっ赤で、体には杉や桧が生え、八つの谷と丘にまたがるほどの大きさ、そしてお腹はいつも血がにじんでただれていると、ただただ大きく恐ろしい姿で『古事記』の一節に書かれています。
しかし、神話に基づくヤマタノオロチの解釈は単なる怪物退治の物語ではありません。この物語の背景にあるものは、古代日本における製鉄技術の発展に伴う自然への影響や、当時の人々の自然への畏怖の情などです。(※たたら集団と大和朝廷との抗争を意味しているという解釈もあるようです)
ヤマタノオロチという架空の大蛇は実は、川の氾濫や洪水といった自然災害を象徴するとされています。
※何度も氾濫を繰り返し、人々を困らせた斐伊川(ひいかわ:島根県を流れる一級河川。源流は出雲市の東部に位置し斐川平野に流れ出て、日本海につながっています)とその支流がヤマタノオロチに例えられていると言われています。
特に、製鉄に必要な砂鉄を川から大量に採取する過程で、川の流れが乱され、川の氾濫が頻発したことが背景にあると考えられます。このような自然災害を、人々は大蛇(ヤマタノオロチ)に見立て神話化し、その恐怖と対峙する物語を作り上げました。
神話の中で、スサノオノミコトはヤマタノオロチを退治する際に、八塩折之酒(やしおりのさけ)という強いお酒を使います。このお酒を飲ませて大蛇を酔わせ、その隙に退治するという戦略を取ります。筆者としては戦いの描写より、神話の時代から高度な酒造りの技術があったのでは?と想像してしまいます。
ヤマタノオロチを退治した後、スサノオノミコトはその尾から天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)を取り出します。この剣は後に草薙剣(くさなぎのつるぎ)と呼ばれ、この剣は、後に皇位の印である「鏡」、「勾玉(まがたま)」と並ぶ、三種の神器となります。古代日本では、鉄の剣は権力や神聖な力を持つ存在とされていました。
3.天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)が示す古代日本の高度な製鉄技術
天叢雲剣の登場は、古代日本における製鉄技術の発展を示す重要な要素です。この物語における剣の登場は、当時の人々が高度な製鉄技術を持っていたという裏付けを示すものと考えられます。鉄が、人間の文明のなかで、金属製品の中心を占め続けた理由は、鉄が地球上に広く分布し、かつ生成法によって多様さをもたせることができる点が理由と思われます。
また当時、製鉄は単なる技術ではなく、神聖な存在であると同時に、生活と密接に結びついたものでもあったのでしょう。
ちなみに「鉄の細工人はこれをつくるのに炭の火をもって細工をし、槌を持ってこれをつくり、強い腕を持ってこれを鍛える」
この言葉・・・実は旧約聖書に書かれている一節なんです。鍛造(たんぞう)が古くから人々の生活に密着していたのは日本だけではないようです。
製鉄に必要な砂鉄は、川の流れに乗って山から運ばれてきます。そのため、川辺での砂鉄採取が盛んに行われました。しかし、砂鉄を大量に採取することは川の流れを変え、時には氾濫を引き起こす原因ともなりました。(ヤマタノオロチの目が真まっ赤だった理由・・・それは錆びた鉄が真っ赤だったから?たたらの炎を見る職人の目が赤く映ったから?溶けた鉄が赤かったから?とその理由を探るだけでも筆者はロマンを感じます。)
こうした洪水の化身とも言うべき自然現象を、古代の人々はヤマタノオロチの神話に投影しました。川の氾濫という恐ろしい自然の力を、大蛇という怪物に見立てることで、その恐怖を具体的に表現したのです。
鉄は武器や工具として生活を豊かにする一方で、その採取や精錬過程で自然環境に与える影響も無視できません。神話におけるヤマタノオロチの物語は、こうした製鉄の持つ二面性を示しているのかもしれません。
台風や水害が近年増え、河川の氾濫はいつどこで発生してもおかしくない時代です。
技術が進歩しても大自然の力の前ではいかに人間は無力であるかを思い知ります。
川上鉄工所は、令和5年度に岡山県BCP認定事業者として認定されました。自然の脅威を侮らず、安定品質の製品を安定供給し続けられるように今後とも努力を続けていきます。
関連記事:たたら製鉄用の砂鉄の種類―真砂砂鉄とは?赤目砂鉄とは?鉄穴流しとは?
桃太郎伝説と製鉄技術との関わりについては、こちらからご覧ください。↓
関連記事:鍛造(たんぞう)の歴史は?桃太郎伝説との関わりは?
川上鉄工所へのお問合せはこちらからお願いいたします!↓
| お問合せ・ご依頼はこちら → |
4.よくある質問(FAQ)
ヤマタノオロチとは、どのような神話ですか?
ヤマタノオロチは、日本神話に登場する8つの頭と8つの尾を持つ大蛇で、スサノオ命が退治したとされる存在です。出雲地方の伝承として有名で、鉄の川=斐伊川との関係性があるとされています。
この神話が「製鉄」と関係あると言われるのはなぜですか?
ヤマタノオロチの「八つの頭と尾」「赤く膨れた目」「体を川のように這う描写」などが、たたら製鉄に必要だった「火・川・鉄鉱石(砂鉄)」のイメージと符合するため比喩的に製鉄を象徴しているという説があります。
「たたら製鉄」とはどのような技術ですか?
たたら製鉄は、日本古来の製鉄法で、砂鉄を木炭とともに炉で加熱し、鉄の塊「鉧(けら)」を作る方法です。火力の調整や風の送り込みに高度な技能が求められました。
スサノオがヤマタノオロチを退治して得た「天叢雲剣」とは?
天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)は、ヤマタノオロチの体内から出てきたとされる伝説の剣で、のちに「草薙剣」として三種の神器の一つになります。これが「製鉄の成果物=鉄剣」を象徴しているとする説もあります。ちなみに、日本書紀における三種の神器は「草薙剣」の他に「八咫鏡 (やたのかがみ)」、「八尺瓊勾玉 (やさかにのまがたま)」があります。
神話を通じて伝えたいことは何ですか?
神話には、古代の職人たちが製鉄技術や鍛造技術に込めた思いが詰まっています。ヤマタノオロチの物語を通じて、川上鉄工所が90年以上大切にしてきた「技術への敬意」「職人の誇り」「挑戦する心」を現代の皆様にも感じていただきたい。古代から受け継がれる「ものづくりの精神」こそが、現代の鍛造技術革新の原動力だと私たちは考えています。
