たたら製鉄用の砂鉄の種類―真砂砂鉄とは?赤目砂鉄とは?鉄穴流しとは?
「たたら製鉄」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。「たたら製鉄」は、主に砂鉄を原料として鋼(はがね)を製造する、日本の伝統的な製鉄法です。
「たたら製鉄」は6世紀頃から行われており、特に日本刀の製造に使われる高品質な鋼である「玉鋼」(たまはがね)の製鉄技術として知られています。
「たたら製鉄」の主原料である砂鉄とは、主に河川や海岸の砂の中に含まれる鉄鉱物の粒子のことです。砂鉄は、鉄を含む鉱石が風化や浸食を受けて細かい粒子となり、川や海に流れ込み、重い鉄鉱物が堆積してできるものです。本コラムでは、ちょっとマニアックな「たたら製鉄」の主原料である砂鉄の種類や採取方法、古代の日本神話との関連性について解説します。
1.たたら製鉄用の砂鉄の種類と製鉄技術
日本では、砂鉄を原料とする「たたら製鉄」が古代から発展し、特に日本刀や農具の製作に重要な役割を果たしました。この原料となる、中国山地で採取される、たたら製鉄用の砂鉄には、実は2種類あることをご存じでしょうか?
その2種類はそれぞれ、真砂砂鉄(まささてつ)と赤目砂鉄(あこめさてつ)と呼ばれ、異なる特徴と用途があります。
(1)真砂砂鉄(まささてつ)とケラ押し法(三日押し)
真砂砂鉄は不純物が少なく、日本刀の原料である「玉鋼」(たまはがね)の製造に適しています。いわば鍛造向きの砂鉄です。真砂砂鉄の産出地は島根県や鳥取県の山陰です。融点は高く、花崗岩、花崗斑岩、黒雲母花崗岩といった岩石に多く含まれています。ちなみに筆者は大学で地質学を専攻しており、花崗岩の判別だけは得意でした(笑)
製鉄過程は「ケラ押し法」という方法が用いられ、この方法では操業開始から終了までに三昼夜、約70時間かかるため、「三日押し」とも呼ばれています。
真砂砂鉄によるケラ押し法は、精錬工程を経ることなく鋼ができる点で、直接的な製鉄法といえます。
(2)赤目砂鉄(あこめさてつ)とズク押し法(四日押し)
赤目砂鉄は真砂砂鉄に比べて不純物が多く、主に「ズク」(銑鉄)として鋳物などに使用されます。鋳造向きの砂鉄です。赤目砂鉄の産出地は岡山県などの山陽側で、東北から九州まで広範囲で採取できます。融点は低く、安山岩、玄武岩、閃緑岩に多く含まれています。
この砂鉄を利用する際には「ズク押し法」という方法が使われ、こちらは操業開始から終了まで四日間、約90時間かかるため「四日押し」と呼ばれます。たたらで得られた銑(ずく)は、そのままでは使えず、処理を施さなければならないので、間接的な製鉄法といえます。
2.鉄穴流し-砂鉄の採取と選鉱
砂鉄の採取は、「鉄穴流し」(かんなながし)と呼ばれる方法が一般的でした。これは、砂鉄の含有量が多い風化した花崗岩(かこうがん)などの山際に水路を導き、山を崩して土砂を水路に流し、選鉱場(せんこうじょう)に運ぶという方法です。
選鉱場では、大池、中池、乙池、そして樋(とい)という順に洗い池を通して、軽い土砂を下流に流し、重い砂鉄を沈殿させて選別しました。
(1) 鉄穴流しの利点
鉄穴流しの利点としては、田畑への転用が進んだことが挙げられます。鉄穴流しで山を崩した後、新しい平地の活用として田畑に転用されました。これらの新しい耕地は、たたら製鉄に関わる人々の食糧を補う重要な資源となりました。
現在、中国山地に残る多くの棚田は、このような鉄穴流しの影響で耕地化されたものと言えます。さらに、砂鉄が埋蔵されている可能性のある場所や鉄穴流しの経路を掘り崩す際には、地域の信仰に関わる場所、例えば墓地や祠、神木などがある土地は避けられていました。
このように人為的に残された丘は「鉄穴残丘」(かんなざんきゅう)と呼ばれ、これらの丘と棚田、段々畑が一体となって、独特の景観を創り出しました。
(2) 鉄穴流しの欠点
鉄穴流しの欠点としては、鉄穴流しによって大量の土砂が河川下流域に流れ込むことが挙げられます。これにより、下流域の農業灌漑用水が土砂で詰まるなど、農業に悪影響を及ぼしました。
人々がより豊かな生活を手に入れるために自然環境を人の手で変え、その結果、自然からしっぺがえしを受ける、というのは、なんとも皮肉な話だなと感じる一方で、創造して破壊することが人類の性なのかもしれません。
環境への配慮:古代から現代へ
鉄穴流しが引き起こした環境問題は、現代の製造業にも重要な教訓を与えています。
スマート鍛造プロセスによる環境負荷低減
川上鉄工所が開発したスマート鍛造プロセス(特許取得)の 最大の特徴は、従来2回必要だった加熱工程を1回に削減したことです
| 項目 | 従来工法 | スマート鍛造プロセス | 削減効果 |
|---|---|---|---|
| 加熱回数 | 2回 | 1回 | 50%削減 |
| 加熱エネルギー | 1200℃×2回 | 1200℃×1回 | 約50%削減 |
| CO2排出量 | 100%(基準) | 約50% | 約50%削減 |
|
生産時間(鋼材入荷から出荷まで) |
100%(基準) | 約70% | 約30%短縮 |
加熱工程を2回から1回に削減するという一見シンプルな改善が、 環境負荷の大幅な低減と生産性向上を同時に実現。これが川上鉄工所の スマート鍛造プロセスです。スマート鍛造プロセスについてはこちらからご覧いただけます → スマート鍛造プロセスの特徴
3.砂鉄採種と古代神話ヤマタノオロチとの関連性
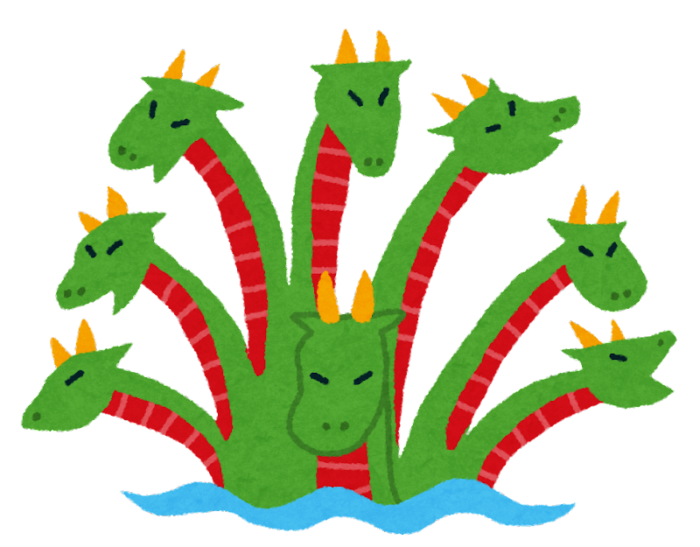
ところで、日本神話には、ヤマタノオロチという怪物が登場します。ヤマタノオロチは、日本神話に登場する巨大な蛇のような怪物で、八つの頭と八つの尾を持っています。古事記に記されているこの神話は、スサノオノミコトがヤマタノオロチを退治してクシナダヒメを救う場面が特に有名です。
この物語は、日本の自然崇拝や土地の神々と人間の関係を示す一方で、ヤマタノオロチという架空の大蛇は実は、川の氾濫や洪水といった自然災害を象徴するとされています。
特に、製鉄に必要な砂鉄を川から大量に獲得する過程で、川の流れが乱され、川の氾濫が頻発したことが背景にあると考えられます。このような自然災害を、人々は大蛇ヤマタノオロチという形で神話化し、その恐怖と対峙する物語を作り上げました。
また、ヤマタノオロチの尾からは、「天叢雲剣」(あまのむらくものつるぎ)という剣が発見されたとされています。古代日本では、鉄の剣は権力や神聖な力を持つ存在とされていました。
ヤマタノオロチの神話と砂鉄は、単に神話上の伝説と製鉄技術だけでなく、自然の力や自然への畏敬を象徴しています。ヤマタノオロチの尾から剣が発見されるという伝説からは、砂鉄から鉄を精錬し、刀剣を作り出す技術的プロセスを象徴していると考えられます。
このように、神話と製鉄技術は、日本の文化や技術の発展に大きな影響を与えてきたのです。
ヤマタノオロチと製鉄の関連性については、以下も合わせてご参照ください。
4. 古代の技術から現代の鍛造技術へ
たたら製鉄で培われた「鍛造」の技術は、現代の川上鉄工所に受け継がれています。
真砂砂鉄から作られた玉鋼が日本刀になったように、現代では チタン鍛造や ステンレス鍛造により、 航空機部品や自動車部品を製造しています。
特に川上鉄工所のスマート鍛造プロセスは、 従来2回必要だった加熱工程を1回に削減し、 CO2排出量を約50%削減。古代の職人が追求した効率性を、 現代技術で実現しています。
ヤマタノオロチと製鉄の関連性については、 こちらの記事も合わせてご参照ください。
よくある質問(FAQ)
Q: たたら製鉄は現在も行われていますか?
A: 島根県の日刀保たたらで年に数回、日本刀製作用の玉鋼生産のために操業されています。 商業的な製鉄としては明治時代に終了しましたが、文化的技術として保存されています。
Q: 真砂砂鉄と赤目砂鉄の違いは何ですか?
A: 真砂砂鉄は不純物が少なく鍛造向き(日本刀用)、赤目砂鉄は不純物が多く鋳造向き(鋳物用)です。 現代の川上鉄工所では、高純度の鋼材を使用し、様々な鍛造製品を製造しています。
Q: 鉄穴流しの技術は現代にも活かされていますか?
A: 直接的な技術継承はありませんが、資源の有効活用という思想は 川上鉄工所の歩留まり85%以上という 高効率生産に受け継がれています。
